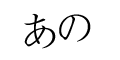2010年08月07日
空想の過去
| 歳をとると、若い頃から持っていた数々の疑問が次第に集約されてくる。この意味では生きててよかったと思う(笑)。「人類はどこの向かっているのか?」はずっとつきまとってた疑問で、そのカギとなるのが過去であり、人類の起源だ。ダーウィンは自らも疑いながら「進化論」を発表し、現代人が妄信する宗教のようになっている。これに年代測定法の「放射性同位体測定法(炭素14)」が加わり、やんややんやの賑わいである。現代人はもはや科学でしか物事を判断することができなくなっている。言い換えれば、科学は現代人にとって「絶対なる宗教」である。まあ、さほどに人間は寄る辺がほしく、「判断基準」をどこかに置きたがる生き物なのだ。とりあえず科学が最もシックリくるというのだろう。ダーウィン自身、こう指摘している。「ある種の生物が別の種の過程を終えて移行したのなら、数え切れないほどの過渡形態の生物が至るところで見られないのは、なぜか? きちんと分類された種を私達は目にしていて、自然界全体の混乱がないのはなぜだろう?この理論によれば、無数の過渡形態[環]が存在してきたはずだが、地殻の中に無数に埋まったそれらの環を発見していないのはなぜか?…すべての生物と絶滅した種の中間にある、中間的な過渡期の環の数は、想像を絶するほどだったに違いない。」過渡形態とは進化する途中の状態のことだ。考古学者が日夜がんばっても出てこない。とりわけボクの疑問は人類の起源に向かう。現在の定説では約200万年前に人類の祖先が誕生し、進化を繰り返し、今の我々になったとされている。ならば、進化の過程で「枝が何本も伸びた」はずで、「人間もどき」がそこらじゅうで見つからなければおかしい。特に「知能」という特徴を持つ人類は他の生物とはかけはなれた優位性をもっているのだから、そう簡単に絶滅するはずがない。例えば、「言葉が多少使えるが読み書きができない、しかし狩猟は天下一品の二足歩行の種族」が今でも野山で生活しているのが自然の流れと言うものだ。自然淘汰を原則とする進化論からすると、サルと人間の中間あたりの「人間もどき」が数え切れないほど現存しているはずだ。百歩譲って、現存していないにしても人間に非常に近い種がもっとたくさん発掘されていなければならない。それとも我々の祖先が「もどき」を皆殺しにしたのだろうか?確かに一部そんな説はあるが、すべての「もどき」を絶滅させるのは難しかったと思う。しかし、現実は人類と称される種は我々だけ。進化論を疑わざるをえない。さらに、現在の人類が有史以来進化しているかというと、それもあやしい。※有史:過去5~6000年とされている。人類の特質が「知性」と「精神性」と「言葉」だとするなら、たまたま科学の発見があったので勘違いしやすいが、どれも進化しているとは言えない。これは人間の歴史を普通に見れば、誰でも分かることだ。むしろ「精神性」においては退化していると言っても過言ではない。特に「言葉」は重大なカギを握っていると思う。有史以来の文献からして、過去の人々が言葉を使う能力において劣っていたとはとても思えない。逆に琵琶法師の例からも分かるように、耳から聞いた言葉を暗記する能力は退化していると言うこともできる。これらを総合すると、一見非科学的に思える「人間は一瞬にして創られ、一瞬にして言葉を与えられた」という説の方がよほど納得がいく。しかし「証明」を絶対条件とする「科学」はこれを否定し、進化論という仮説を証明しようとするができなくて、迷路に迷い込んでいるというのが現状だ。その証明手段の最たるものに、先ほどの「放射性同位体測定法」があるが、これもまた地球上の環境が宇宙線などを含め一定条件に保たれていたという前提が必要になる。従って、この測定法の危うさを指摘する声も多い。もしかすると、科学が唱える過去は単なる「空想の過去」なのかも知れない。アインシュタインが物理学者の立場から興味深いことを言っている。「我々は今や核分裂と核融合の原理を知っているので、我々の知るこの地球が一瞬の内に存在した可能性があることにも気づいている。」若い人や興味のない人は「そんなのどっちでもいいじゃん!」と思うだろうし、理解もできる。 しかし、現在世界中で起きている多くの問題を解くカギは、こんなところにあると思えてならない。 |









 もっと知りたい!
安くする方法
もっと知りたい!
安くする方法