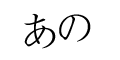2010年08月30日
現在ある社会保障
【問い合わせ先】株式会社 保険プラザ
無料証券分析について

【医療保険】
1.現在ある社会保障
2.医療保険不要論
3.医療保険の保険料を決定づけるもの:①10年更新タイプと終身タイプ
4.医療保険の保険料を決定づけるもの:②連続入院日数
5.入院給付金
6.手術給付金
7.その他、特約など
1.現在ある社会保障
①高額療養費制度
医療費の自己負担が高額になったとき、1ヶ月に一定の金額(自己負担額)を超えた部分を払い戻してもらえます。
70歳未満で平均的収入(月額報酬53万円以下、かつ住民税を納めている方)の場合。
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%
具体的に、総医療費が100万円かかったとしましょう。
3割負担ですから、窓口では30万円ですね。
しかし、この制度があるので、
80,100円+(100万円ー267,000円)×1%=87,430円が自己負担額。
だから、一旦30万円払ったとしても、差額の212,570円は戻ってきます。
※最近は窓口で最初から相殺してくれる病院も増えてきています。
大ざっぱに言って、一ヶ月に9万円あれば医療費はこと足りることになります。
②医療費控除
これは、一定以上の医療費がかかった場合、課税所得からその分が控除されるものです。
1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費が10万円(課税所得が200万円未満の場合は課税所得の5%)を超えた場合、所得から10万円を超えた医療費を差し引いた分が課税されます。
生計を一にする家族全員の医療費を合計して、家族のうちの一人の所得から差し引くことができます。
通院時のバス代や電車代は医療費控除の対象となりますが、医療行為でも美容や予防目的の費用は対象になりません。
申告のためには交通費のメモや医療費の領収書を保存しておくことが大切です。
分からないことは税務署に問い合わせましょう。
③傷病手当
病気やけがで会社を休まなければならないとき、生活を保護するために給付されるのが傷病手当です(国民健康保険にはこの制度がありません)。
勤務先を連続して休んだ日の4日目以降から給付され、金額は給料の3分の2程度です。
病気やけがで休んでも、勤務先から給料やその一部が支払われる場合は、傷病手当金は減額されたり、支払われないことがあります。
詳細は、加入している健康保険組合や年金事務所、勤務先の担当部署に問い合わせてください。
④障害年金
これは、病気やけがで重い障害を負い、仕事が出来ないほど日常生活や活動範囲が制限されたときに支給される年金です。
給付を受けるには障害認定を受ける必要があります。
また、国民年金や厚生年金の保険料納付状態など条件はいろいろありますが、ガンでも障害年金がもらえることはあまり知られていません。
市区町村役場、役所や年金事務所で相談に応じてくれます。
⑥介護保険制度
これは、ガンで介護が必要になった場合にも利用できる公的サービスです。
在宅サービスとして、訪問介護や看護、訪問入浴、住宅改造の費用や福祉機器購入費の支給などがあります。
サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があり、要介護状態の区分によって保険で利用できる月ごとの給付費用の上限が異なります。
対象は40歳以上の介護保険の被保険者で、64歳までの方は「末期ガン」という条件がありますが、病状が進んで生活に支障が出た場合と考えればよいでしょう。
市区町村の担当窓口などに相談してみましょう。
⑥療養費払いの制度
医師の指示で治療に必要なコルセットなどの治療器具などを購入したとき、いったんはその費用を全額支払いますが、申請すれば公的な医療保険の給付分が払い戻されます。
子宮がんや乳がんの治療後のむくみ予防のための弾性ストッキングや男性スリーブにも、この制度が適用されます。
一度に2枚しか認められませんが(半年後再申請できる)、1枚2~3万円する製品もあるので、積極的に利用したいものです。
利用するには、医療機関からの指示書や領収書を添付して、加入している公的医療保険者(健康保険組合など)に申請書を提出します。
⑦後期高齢者医療制度
老人に対する医療費問題は我が国の最重要課題で、制度が目まぐるしく変わってきています。
非常に安定感に乏しい制度と言わざるをえません。
詳しくはこちらをどうぞ。
前回、我が国の現状について触れましたが、それを踏まえたうえで、これらの制度が将来どう変わっていくでしょうか?
誰も分からないことなので、みなさんに投げかけるしかありません。
制度そのものが危ういとするなら、「問題あり」と言える医療保険が現在多く存在します。
①日本人が最も多く加入している医療保険の保障期間は最長で80歳まで。
②ある保険会社のコンサルティングでは、過去の老人医療制度を前提に、医療保険の保障期間を70歳までとしている。
医療保険に加入するとするなら、どちらもよく考える必要がありますね。
【問い合わせ先】株式会社 保険プラザ
無料証券分析について
無料証券分析について

【医療保険】
1.現在ある社会保障
2.医療保険不要論
3.医療保険の保険料を決定づけるもの:①10年更新タイプと終身タイプ
4.医療保険の保険料を決定づけるもの:②連続入院日数
5.入院給付金
6.手術給付金
7.その他、特約など
1.現在ある社会保障
①高額療養費制度
医療費の自己負担が高額になったとき、1ヶ月に一定の金額(自己負担額)を超えた部分を払い戻してもらえます。
70歳未満で平均的収入(月額報酬53万円以下、かつ住民税を納めている方)の場合。
80,100円+(総医療費ー267,000円)×1%
具体的に、総医療費が100万円かかったとしましょう。
3割負担ですから、窓口では30万円ですね。
しかし、この制度があるので、
80,100円+(100万円ー267,000円)×1%=87,430円が自己負担額。
だから、一旦30万円払ったとしても、差額の212,570円は戻ってきます。
※最近は窓口で最初から相殺してくれる病院も増えてきています。
大ざっぱに言って、一ヶ月に9万円あれば医療費はこと足りることになります。
②医療費控除
これは、一定以上の医療費がかかった場合、課税所得からその分が控除されるものです。
1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費が10万円(課税所得が200万円未満の場合は課税所得の5%)を超えた場合、所得から10万円を超えた医療費を差し引いた分が課税されます。
生計を一にする家族全員の医療費を合計して、家族のうちの一人の所得から差し引くことができます。
通院時のバス代や電車代は医療費控除の対象となりますが、医療行為でも美容や予防目的の費用は対象になりません。
申告のためには交通費のメモや医療費の領収書を保存しておくことが大切です。
分からないことは税務署に問い合わせましょう。
③傷病手当
病気やけがで会社を休まなければならないとき、生活を保護するために給付されるのが傷病手当です(国民健康保険にはこの制度がありません)。
勤務先を連続して休んだ日の4日目以降から給付され、金額は給料の3分の2程度です。
病気やけがで休んでも、勤務先から給料やその一部が支払われる場合は、傷病手当金は減額されたり、支払われないことがあります。
詳細は、加入している健康保険組合や年金事務所、勤務先の担当部署に問い合わせてください。
④障害年金
これは、病気やけがで重い障害を負い、仕事が出来ないほど日常生活や活動範囲が制限されたときに支給される年金です。
給付を受けるには障害認定を受ける必要があります。
また、国民年金や厚生年金の保険料納付状態など条件はいろいろありますが、ガンでも障害年金がもらえることはあまり知られていません。
市区町村役場、役所や年金事務所で相談に応じてくれます。
⑥介護保険制度
これは、ガンで介護が必要になった場合にも利用できる公的サービスです。
在宅サービスとして、訪問介護や看護、訪問入浴、住宅改造の費用や福祉機器購入費の支給などがあります。
サービスを利用するには、要介護認定を受ける必要があり、要介護状態の区分によって保険で利用できる月ごとの給付費用の上限が異なります。
対象は40歳以上の介護保険の被保険者で、64歳までの方は「末期ガン」という条件がありますが、病状が進んで生活に支障が出た場合と考えればよいでしょう。
市区町村の担当窓口などに相談してみましょう。
⑥療養費払いの制度
医師の指示で治療に必要なコルセットなどの治療器具などを購入したとき、いったんはその費用を全額支払いますが、申請すれば公的な医療保険の給付分が払い戻されます。
子宮がんや乳がんの治療後のむくみ予防のための弾性ストッキングや男性スリーブにも、この制度が適用されます。
一度に2枚しか認められませんが(半年後再申請できる)、1枚2~3万円する製品もあるので、積極的に利用したいものです。
利用するには、医療機関からの指示書や領収書を添付して、加入している公的医療保険者(健康保険組合など)に申請書を提出します。
⑦後期高齢者医療制度
老人に対する医療費問題は我が国の最重要課題で、制度が目まぐるしく変わってきています。
非常に安定感に乏しい制度と言わざるをえません。
詳しくはこちらをどうぞ。
前回、我が国の現状について触れましたが、それを踏まえたうえで、これらの制度が将来どう変わっていくでしょうか?
誰も分からないことなので、みなさんに投げかけるしかありません。
制度そのものが危ういとするなら、「問題あり」と言える医療保険が現在多く存在します。
①日本人が最も多く加入している医療保険の保障期間は最長で80歳まで。
②ある保険会社のコンサルティングでは、過去の老人医療制度を前提に、医療保険の保障期間を70歳までとしている。
医療保険に加入するとするなら、どちらもよく考える必要がありますね。
【問い合わせ先】株式会社 保険プラザ
無料証券分析について









 もっと知りたい!
安くする方法
もっと知りたい!
安くする方法