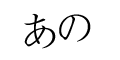2010年09月14日
ペイオフ発動、国内初
「時事ドットコム」の記事。
保護対象外は3423人の110億円=振興銀預金の名寄せ終了-預保機構
日本振興銀行(東京都千代田区)の金融整理管財人の預金保険機構は12日、同行の同一人物の預金を取りまとめる「名寄せ」作業を終了した。経営破綻(はたん)した10日時点の預金残高5820億円のうち、預金保険で保護されない1000万円を超える預金は、全預金者の2.7%に当たる3423人が持ち、総額110億円と判明した。
預保機構は、預金の払い戻し原資などに充てるため日銀から資金を借り入れ、振興銀に対して約6000億円を上限とした貸し付けを行う。保護対象外の預金者らを対象とした債権者説明会は週内にも開催される予定。(2010/09 /12-18:33)
被害を受けた方々は大変気の毒ですが、
これは自己責任ですね。
同様に保険加入も、
自己責任です。
保護対象外は3423人の110億円=振興銀預金の名寄せ終了-預保機構
日本振興銀行(東京都千代田区)の金融整理管財人の預金保険機構は12日、同行の同一人物の預金を取りまとめる「名寄せ」作業を終了した。経営破綻(はたん)した10日時点の預金残高5820億円のうち、預金保険で保護されない1000万円を超える預金は、全預金者の2.7%に当たる3423人が持ち、総額110億円と判明した。
預保機構は、預金の払い戻し原資などに充てるため日銀から資金を借り入れ、振興銀に対して約6000億円を上限とした貸し付けを行う。保護対象外の預金者らを対象とした債権者説明会は週内にも開催される予定。(2010/09 /12-18:33)
被害を受けた方々は大変気の毒ですが、
これは自己責任ですね。
同様に保険加入も、
自己責任です。
2010年09月14日
【学資保険】
【問い合わせ先】株式会社 保険プラザ
証券分析について

<用語が分からない時>
【生命保険用語集】
今回から、各保険会社でさまざまな名前がついている代表的な商品の説明をします。
そのためには、私の過去ブログの「生命保険の3つの基本形」を理解しておいた方が、より分かりやすいと思います。
「生命保険の3つの基本形」
「定期保険」
「終身保険」
「養老保険」
「学資保険」は上記の「養老保険」に該当します。
保険商品はこのように基本形を変形させ名前をつけているのですが、この「学資保険」というネーミングは最高傑作だと私は思っています(笑)。
だって、出産したら入るのが当然のような意識付けに成功していますよね。
「養老保険」の記事の中にも書きましたが、現在は利率が大変悪くなっていて、多くの「養老保険」が元本割れを起こしています。
従って、「学資保険」も元本割れが多くなっているのですが、保険会社によっては元本を上回ることもあります。
※私はブログ上では、保険会社と商品名は一切出しませんが、個別に質問されればきちんとお答えします。
さて、仕組みです。
【契約形態】
【保障】
■一般的には大学入学時をゴールとします。
子どもの生まれ月によって、受け取りを17歳のするか18歳にするかを判断します。
■大学入学時だけでなく、中学や高校入学時に少しずつ受け取れる設計も出来ます。
しかし、その場合18歳で一度に受け取る設計と比べると、総受取額が少なくなります。
【注意点】
■ある家庭の保険証券を分析すると、親の保障に対する保険料より子どもに対する保険料がはるかに大きいことがあります。
気持ちは分かりますが、保障には優先順位があります。
親の保障をきちんとしてから、次に「学資」を考える、これが原則です。
■大学入学時100万円~200万円の設計が多いですが、これは入学金に充てるもので、以後の授業料や下宿代はさらに必要です。
■祝い金や満期金は、必要がなくても強制的に支払われる。
子どもが進学しない場合や、おじいちゃんから思わぬ援助があることも考えられます。
満期金を受け取って怒る人はいないでしょうが、ここはちょっと待った!です。
学資として受け取った金額が200万円、これを受け取らないでそのままにしておいたら、
さらに10年後250万円になるとしたらどうでしょうか?
以前にも書きましたが、長期的運用では保険が圧倒的に有効です。
必要がなければ、さらに増やして親の老後に充てるという考え方が、これからは大切です。
■特約で子どもの入院保障をつけるかどうか?
先にも書きましたが、親の保障をきちんとした後で余裕資金があればつけてもいいでしょう。
しかし、優先順位としては親の保障をさらに充実させる方が理にかなっています。
なぜなら、子どもが入院しても、親が元気で働いてさえいれば、大きな経済リスクは発生しないからです。
【学資保険以外の方法】
まず最近の学資保険のデメリットを整理します。
・低金利の影響で元本割れか、増えても僅か。
・必要がなくても強制的に支払われる。
これに対し、ある方法では、
・学資保険の機能も備えながら、
・学資保険よりもお金を増やし、
・必要がなければ据え置いてさらに増やし、
・同時に親の保障を確保できる
ことが可能です。
これは、どこから見ても学資保険より優っている方法ですが、紙面上別の機会に説明します。
【問い合わせ先】株式会社 保険プラザ
証券分析について
証券分析について

<用語が分からない時>
【生命保険用語集】
今回から、各保険会社でさまざまな名前がついている代表的な商品の説明をします。
そのためには、私の過去ブログの「生命保険の3つの基本形」を理解しておいた方が、より分かりやすいと思います。
「生命保険の3つの基本形」
「定期保険」
「終身保険」
「養老保険」
「学資保険」は上記の「養老保険」に該当します。
保険商品はこのように基本形を変形させ名前をつけているのですが、この「学資保険」というネーミングは最高傑作だと私は思っています(笑)。
だって、出産したら入るのが当然のような意識付けに成功していますよね。
「養老保険」の記事の中にも書きましたが、現在は利率が大変悪くなっていて、多くの「養老保険」が元本割れを起こしています。
従って、「学資保険」も元本割れが多くなっているのですが、保険会社によっては元本を上回ることもあります。
※私はブログ上では、保険会社と商品名は一切出しませんが、個別に質問されればきちんとお答えします。
さて、仕組みです。
【契約形態】
- 契約者(保険料を払うヒト)→親
- 被保険者(保険が掛かるヒト)→子供
- 祝い金・満期金の受取人→親
- 死亡保険金(子供の死亡)の受取人→親
【保障】
■契約者である親が亡くなると、以後保険料の支払はなくなり、祝い金・満期金は予定通り受取れます。
■子供が亡くなった場合、少額ですが親に死亡保険金が支払われます。
■一般的には大学入学時をゴールとします。
子どもの生まれ月によって、受け取りを17歳のするか18歳にするかを判断します。
■大学入学時だけでなく、中学や高校入学時に少しずつ受け取れる設計も出来ます。
しかし、その場合18歳で一度に受け取る設計と比べると、総受取額が少なくなります。
【注意点】
■ある家庭の保険証券を分析すると、親の保障に対する保険料より子どもに対する保険料がはるかに大きいことがあります。
気持ちは分かりますが、保障には優先順位があります。
親の保障をきちんとしてから、次に「学資」を考える、これが原則です。
■大学入学時100万円~200万円の設計が多いですが、これは入学金に充てるもので、以後の授業料や下宿代はさらに必要です。
■祝い金や満期金は、必要がなくても強制的に支払われる。
子どもが進学しない場合や、おじいちゃんから思わぬ援助があることも考えられます。
満期金を受け取って怒る人はいないでしょうが、ここはちょっと待った!です。
学資として受け取った金額が200万円、これを受け取らないでそのままにしておいたら、
さらに10年後250万円になるとしたらどうでしょうか?
以前にも書きましたが、長期的運用では保険が圧倒的に有効です。
必要がなければ、さらに増やして親の老後に充てるという考え方が、これからは大切です。
■特約で子どもの入院保障をつけるかどうか?
先にも書きましたが、親の保障をきちんとした後で余裕資金があればつけてもいいでしょう。
しかし、優先順位としては親の保障をさらに充実させる方が理にかなっています。
なぜなら、子どもが入院しても、親が元気で働いてさえいれば、大きな経済リスクは発生しないからです。
【学資保険以外の方法】
まず最近の学資保険のデメリットを整理します。
・低金利の影響で元本割れか、増えても僅か。
・必要がなくても強制的に支払われる。
これに対し、ある方法では、
・学資保険の機能も備えながら、
・学資保険よりもお金を増やし、
・必要がなければ据え置いてさらに増やし、
・同時に親の保障を確保できる
ことが可能です。
これは、どこから見ても学資保険より優っている方法ですが、紙面上別の機会に説明します。
【問い合わせ先】株式会社 保険プラザ
証券分析について









 もっと知りたい!
安くする方法
もっと知りたい!
安くする方法